今月のイチオシ本

『寄席放浪記』 色川武大 (廣済堂文庫)
岡本 敏則
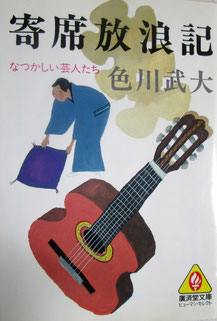
昨年10月7日、柳屋小三治は81年の生涯を閉じた。1959年5代目小さんに弟子入り、1963年二つ目、1969年真打に昇進した。特に噺に入る前の「まくら」が人気で、「まくら」だけ聞きに来るというファンもいた。晩年は難病を抱えながらも全国を公演していた。「独演会」のチケットはプラチナチケットで、手に入れるのは難しかった。
筆者も落語は好きで、荻窪在なので丸の内線でよく「新宿末広」に通っていた。寄席の割り前は微々たるものではあるが小三治は律義に「とり」として出演していた。独演会では1000人2000人というホールでやれば、入場料4500円として、主催者と半々として、数百万の収入になる。同じ新宿の「紀伊国屋」は月一で「紀伊国屋寄席」主宰し、そこは30分と持ち時間も長いので噺家もやる気の出る寄席であった。筆者は「つて」があり、毎回いい席がとれた。小三治はそこでよく聴いた。それにしても惜しい噺家であった。師匠の小さんも最晩年聴いた。「セシオン杉並」で、その時は話の途中で間があき、みんな固唾をのんで続きを待った。聴衆は小さんを目に焼き付けたかったのだ。レジェンドとして。
色川武大(1929~1989)は新宿牛込矢来町の生まれで、子供のころから近くの神楽坂の寄席によく通った。父親は退役軍人で寄席好きでよく連れていかれたという。色川は学校になじめずよくさぼって浅草や都内の小芝居までよく見ていたという。本人は演らないが「観る目」だけは肥えた。子供時代の夢は寄席の席亭になることだった。自分で割り(番組)を創ってお客に観せる、そういうことに憧れていた。色川にはもう一つ阿佐田哲也という筆名がある。自身雀士で徹マンも多く「アサダテツヤ」をもじったものだという。『麻雀放浪記』が一番有名かもしれない。
◎文楽と志ん生=「つくづく思うけれども、昭和の落語家では桂文楽(八代目1892~1971)と古今亭志ん生(五代目1890~1973)が抜き出た存在だな。その最も大きな理由は、二人ともそれぞれのやり方で、自分の落語を創り上げたことにあると思う。古典の方に自分から寄っていってしがみつくのではなく、自分の方に古典落語を引っ張り寄せた。古典というのは(落語に限らず)前代の口跡をただ継承しているだけでは、古典の継承にはならない。前代のコピーでは必ずいつか死滅するか、無形文化財のようなものと化して烈しい命脈を失ってしまう。リレーというものはそうではないので、その時代に応じて新しい演者が、それぞれの個性、それぞれの感性で活かし直していく、それではじめて古典が伝承されていくのである。(文楽の噺)は権力機構からかはずれた庶民、特に街の底辺に下積みで暮らさざるを得ない下層庶民の口惜しさ、切なさが、どの演目(「寝床」「素人鰻」「明烏」)にもみなぎっている。その切なさの極が形式に昇華されて笑いになっている」。志ん生の「まくら」にこういうのがある。「今は目が慣れてないから駄目ですな。すぐ転んじゃう、電車(都電)の安全地帯なんかつまずいて、またあそこは固いものばかりだからね。うっかりそんなところを歩くと、おいあぶねえよ、そこは安全地帯だから―、なんて」。
閑話休題―八代目の弟子で当代の文楽から寄席で聞いた話。「先代の文楽は謹厳実直と思うでしょう、師匠のお供でとあるお大尽に呼ばれて一席話して、ご祝儀をたっぷりいただいて、そしたら師匠、別室で指に唾つけて札を数えてるんですよ」
◎柳寿美夫という芸人=戦争終末期、新宿伊勢丹横の焼けて外側だけ残ったような映画館での柳の漫談「アメリカなんてチョロイもんです。何しろ親方がルーズベルトですから、ルーズは英語で、たるんだ、とか、のびたとかいう意味で、たるんだベルトなんかどうにもなりません」。敗戦後すぐまた見に行くと柳は同じ出し物をまだ続けており「撃ちてしやまんーは昨日までのことでして、いまはトルーマンです。アメリカはいいですな、自由の国です。トルーは真実、真実の人が親方なんですから」。
「利根の川風袂に入れて~の玉川勝太郎」「旅行けば駿河の国に茶の香り~の廣澤虎造」「山のあなあな~の三代目三遊亭圓歌」「綴り方狂室の四代目柳亭痴楽」「どうもすいません~の先代林家三平」「野太い声の三代目三遊亭金馬」、「NHKお笑い三人組の一龍齋貞鳳、三遊亭小金馬、江戸屋猫八」、懐かしい芸人たちだ。
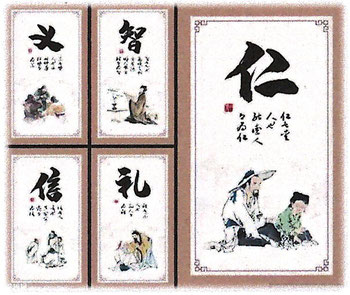
社会の調和と安泰に必要な五常の徳は、「仁・義・礼・智・信」だと儒教が教えている。なかでも重要なのが「仁」と「義」である。それは人間が守るべき道徳で、礼儀上なすべき努めのことである。日本人が大切にしている基本的な価値観でもある。
10月10日、公明党は政権を離脱した。
公明党は連立維持の条件として「靖国神社参拝」「裏金問題の解明」「企業献金問題」の対応を連立維持の条件としていたが、これらに対して自民党から明確な回答がなかったからだとしているが、自民党は「一方的に告げられた」と言っている。
私は、公明党が連立の条件を出したとき、その条件に一瞬「今さら?」という気がした。連立を組んで26年、その間、それらは何度も問題になったはずである。それを容認(?)してきたのに、なぜ、今になってそれを頑なに主張するのかと思ったのだ。だが、それは、民意に押されているからだと好意的に解釈していた。
自民党の党大会で、高市早苗が総裁になり、麻生太郎が副総裁になった。常識的に考えると、新総裁はいの一番に連立を組んできた公明党に挨拶に出向き、その上で「今後、どうしましょうか?」と相談するのが筋であろう。
だが、そうではなかった。高市と麻生が最初に会ったのが、国民民主党代表の玉木雄一郎だったのだ。当然、政権協力の話をしたのだろう。
「仁」と「義」に続くのが「礼」である。これも日本人の基本的な価値観で、日本人はこれらに欠ける人間を徹底的に嫌う。
自民党は、支えてくれた公明党に「仁義」も「礼節」も示さなかった。公明党からすればそれは侮蔑されたことであり、屈辱と怒りを感じたはずである。私だって相手がそういう人間なら、さっさと見切りをつけて縁を切るはずだ。
1973(昭和48)年『仁義なき戦い』という映画があった。シリーズで5作創られ、1999(平成11)年「日本映画遺産200」にも選ばれている。
ヤクザを主人公にしているが、ヤクザ映画でも任侠映画でもない。義理と人情、恩義と裏切り、愛と憎悪、怨念と殺戮を描いた群衆活劇で、戦後日本の暗黒社会を描いていた。
石破首相の退陣から総裁選、新総裁誕生と今までの政局をみていると、権力を握るための打算と工作、陰で暗躍する長老たちばかりが目につく。映画は「仁義なき社会は抗争を生む」といっていたが、自民党内部はまるでこの映画のようである。
かつて、自民党と有権者は、政策より義理と人情でつながっているといわれていた。そのころの自民党には、まだ「仁・義・礼」もあったということだろうが、今はカネがすべてのようだ。「五常」の残るは「智(道理をよく知り、知識が豊富)」と「信(情に厚く真実を告げ約束を守る)」だが、自民党はそれさえも失ってはいないか。