損保経営者は薦めそうもない本

布留川正博『奴隷船の世界史』岩波新書
奴隷貿易と保険業の深い関係
岡本敏則
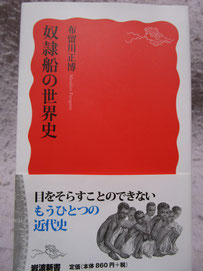
「我々はメイフラワー号でこの国に来たのではない。奴隷船で連れてこられたのだ」
これは1965年暗殺された米国公民権活動家マルコム・Xの言葉だ。12世紀~14世紀、イスラーム世界はヨーロッパよりも優れた学問や技術、産物を持っていた。ヨーロッパの知識人はイスラーム世界に対し大いなる劣等感を抱き、これを払拭するために大航海時代に乗り出していった。航海術、造船技術が飛躍的に向上し、それが奴隷貿易の引き金になった。1441年ポルトガルが最初の奴隷船を出航させた。イギリス・フランス・スペイン・オランダなどが続き、出航地はリヴァプール、ナント、カディス、アムステルダム、リスボンなど。西アフリカの風上海岸、黄金海岸(現在のナイジェリア、カメルーン、ガーナ、ギニア、セネガル、シエラ・レオネなど)でアフリカ人を調達した。貿易先は南北アメリカ、カリブ海の島々。現在の米合衆国、ブラジル、ベネズエラ、ガイアナ、キューバ、ハイチ、ジャマイカ、プエルト・リコなど。何人ぐらいのアフリカ人が奴隷として連れてこられたのか、米国歴史家のカーテインによれば1000万人超。奴隷船の大きさは、100~200屯。長さは24~27m、幅が6~7.5m。そこに数百人の奴隷を積み込んだ。男性奴隷は下甲板、平甲板に2人づつ手首足首を鎖でつながれ寝かされていた。ちなみに「遣唐使船」(630~894年)は平均300屯で長さは30mであった。
奴隷船は「移動する監獄」、「浮かぶ牢獄」と呼ばれ、2カ月以上に及ぶ航海中は毎日16時間以上身動き一つできず板の上に寝かせられていた。航海中は伝染病を防ぐために何度か海水や酢、煙草の煙によって洗浄された。「商品」である奴隷の死亡を出来る限り少なくするという「経済効率」のためであった。奴隷貿易の出資者は、貴族、商人、聖職者、地主などで、奴隷は「積荷」として保険(英国のロイズなど)がかけられた。
保険業の発展は奴隷貿易と密接なかかわりを持っていた。1771年英国籍のゾング号事件が起きた。440人の奴隷をすし詰めにしたゾング号は伝染病で60人の奴隷が犠牲となった。感染の拡大を恐れた船長は「自然死の奴隷は船主の損失となる。生きたまま海に投げ込めば保険会社の損失となる」と114人の奴隷の手を縛り海に投げ捨てた。英国に帰港したゾング号の船主は奴隷一人当たり30ポンドの保険支払いを裁判に訴えたが敗訴。これが奴隷貿易禁止の世論となった。奴隷解放運動の担い手は、クウェイカー教徒と英国国教会福音主義派であった。奴隷貿易は1866年キューバでの禁止により400年の幕を閉じた。が、現在も奴隷がいる。動産奴隷制、債務奴隷制、契約奴隷制で全世界で4580万人と報告されている。
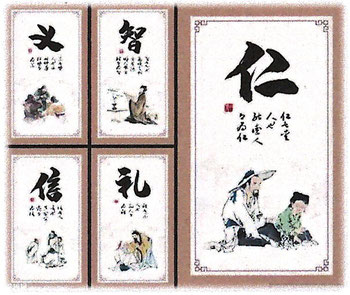
社会の調和と安泰に必要な五常の徳は、「仁・義・礼・智・信」だと儒教が教えている。なかでも重要なのが「仁」と「義」である。それは人間が守るべき道徳で、礼儀上なすべき努めのことである。日本人が大切にしている基本的な価値観でもある。
10月10日、公明党は政権を離脱した。
公明党は連立維持の条件として「靖国神社参拝」「裏金問題の解明」「企業献金問題」の対応を連立維持の条件としていたが、これらに対して自民党から明確な回答がなかったからだとしているが、自民党は「一方的に告げられた」と言っている。
私は、公明党が連立の条件を出したとき、その条件に一瞬「今さら?」という気がした。連立を組んで26年、その間、それらは何度も問題になったはずである。それを容認(?)してきたのに、なぜ、今になってそれを頑なに主張するのかと思ったのだ。だが、それは、民意に押されているからだと好意的に解釈していた。
自民党の党大会で、高市早苗が総裁になり、麻生太郎が副総裁になった。常識的に考えると、新総裁はいの一番に連立を組んできた公明党に挨拶に出向き、その上で「今後、どうしましょうか?」と相談するのが筋であろう。
だが、そうではなかった。高市と麻生が最初に会ったのが、国民民主党代表の玉木雄一郎だったのだ。当然、政権協力の話をしたのだろう。
「仁」と「義」に続くのが「礼」である。これも日本人の基本的な価値観で、日本人はこれらに欠ける人間を徹底的に嫌う。
自民党は、支えてくれた公明党に「仁義」も「礼節」も示さなかった。公明党からすればそれは侮蔑されたことであり、屈辱と怒りを感じたはずである。私だって相手がそういう人間なら、さっさと見切りをつけて縁を切るはずだ。
1973(昭和48)年『仁義なき戦い』という映画があった。シリーズで5作創られ、1999(平成11)年「日本映画遺産200」にも選ばれている。
ヤクザを主人公にしているが、ヤクザ映画でも任侠映画でもない。義理と人情、恩義と裏切り、愛と憎悪、怨念と殺戮を描いた群衆活劇で、戦後日本の暗黒社会を描いていた。
石破首相の退陣から総裁選、新総裁誕生と今までの政局をみていると、権力を握るための打算と工作、陰で暗躍する長老たちばかりが目につく。映画は「仁義なき社会は抗争を生む」といっていたが、自民党内部はまるでこの映画のようである。
かつて、自民党と有権者は、政策より義理と人情でつながっているといわれていた。そのころの自民党には、まだ「仁・義・礼」もあったということだろうが、今はカネがすべてのようだ。「五常」の残るは「智(道理をよく知り、知識が豊富)」と「信(情に厚く真実を告げ約束を守る)」だが、自民党はそれさえも失ってはいないか。